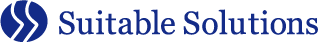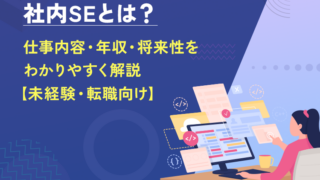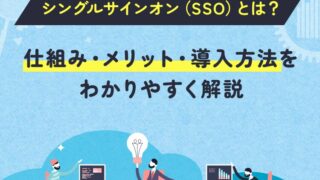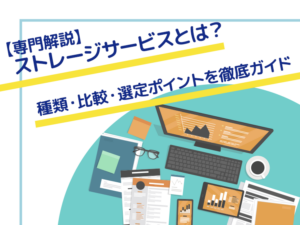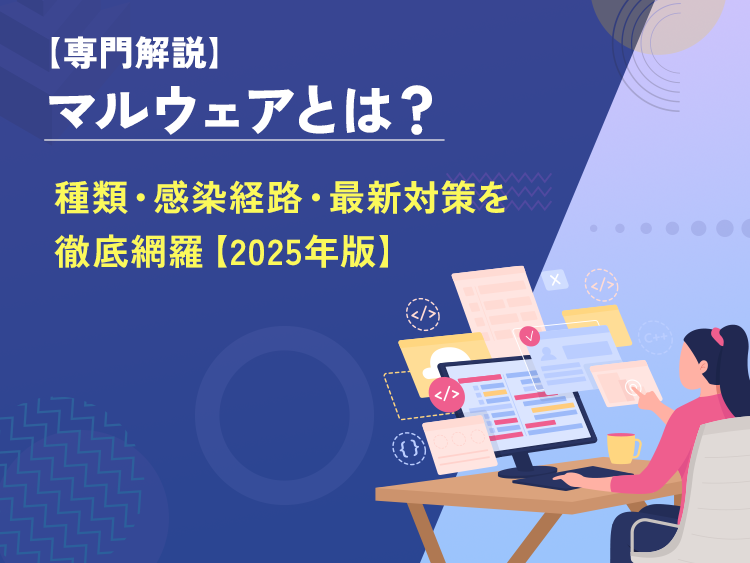
【専門解説】マルウェアとは?種類・感染経路・最新対策を徹底網羅【2025年版】
サイバー攻撃の脅威が年々増大するなか、企業・個人を問わず最も身近で深刻なリスクが「マルウェア(Malware)」です。
マルウェアとは “malicious(悪意のある)” と “software(ソフトウェア)” を組み合わせた言葉で、情報窃取・破壊・不正操作などを目的とする悪意のあるプログラム全般を指します。
従来の「ウイルス」とは異なり、マルウェアは多様化・高度化しています。たとえば、感染後に身代金を要求する「ランサムウェア」や、AIを悪用して防御をすり抜ける「ファイルレス型」など、その形態は日々進化しています。
本記事では、マルウェアの基本定義から種類・感染経路・検知方法・除去手順・企業における防御対策・2025年の最新トレンドまでを体系的に解説。
SOC/CSIRTメンバー、情報システム担当者、セキュリティエンジニアはもちろん、「ウイルスとの違いを理解したい一般ユーザー」にも役立つ、専門性と実用性を両立した内容です。
目次
マルウェアとは?基本定義と概念
「マルウェア」と「ウイルス」の違い
「マルウェア」は、悪意を持って設計されたプログラム全体を指す総称です。
一方「ウイルス」は、マルウェアの中でも「自己増殖し、他のプログラムに寄生する」タイプを意味します。
つまり、マルウェアには以下のような多様な亜種が含まれます。
- ウイルス(Virus)
- ワーム(Worm)
- トロイの木馬(Trojan Horse)
- スパイウェア/アドウェア
- ランサムウェア
- ルートキット/バックドア/ボットネット
すべて「悪意ある挙動を行うソフトウェア」であり、感染経路や目的により分類されます。
マルウェアの目的(情報窃取/破壊/金銭目的など)
マルウェアの背後には攻撃者の明確な目的があります。代表的なカテゴリは以下の通りです。
| 目的 | 内容 | 被害例 |
|---|---|---|
| 情報窃取 | ID・パスワード・顧客データ・社内資料を盗む | 認証情報漏えい、情報流出 |
| 金銭目的 | ランサムウェアでの身代金要求、広告クリック詐欺 | システム停止、金銭損失 |
| 破壊・妨害 | サーバ破壊、業務停止、DDoS攻撃 | サービス停止、顧客信頼失墜 |
| スパイ活動 | 国家・企業を狙う持続的標的型攻撃(APT) | 情報戦・産業スパイ行為 |
攻撃者は必ずしも「愉快犯」ではなく、金銭・政治的動機を持つ組織的犯罪が増加しています。
マルウェアが進化してきた背景と歴史的経緯
1986年に登場した「Brainウイルス」から始まり、2000年代には「ILOVEYOU」ワームが世界中に感染。
2010年代以降は「ランサムウェア(WannaCry)」や国家支援型の「Stuxnet」が登場し、社会インフラを狙う攻撃も現れました。
2020年代に入り、クラウド化・テレワークの普及により攻撃対象は分散し、EDR/XDRなどの新防御技術が登場するなど、防御と攻撃のいたちごっこが続いています。
マルウェアの主な種類と特徴
ウイルス(Virus)
他のプログラムに寄生して自己増殖し、感染を広げるタイプ。感染媒体はメール添付やUSBが中心で、感染後にファイル破壊・システム改変を行います。古典的なタイプですが、依然として多くの派生型が存在します。
ワーム(Worm)
ネットワークを通じて自動的に拡散する自己増殖型マルウェアです。感染経路を必要とせず、脆弱なサーバや端末を探して侵入します。
「Code Red」「Conficker」などが代表例で、企業ネットワークを一気に麻痺させる危険性があります。
トロイの木馬(Trojan Horse)
正規ソフトウェアを装って侵入し、内部でバックドアを設置するタイプ。ユーザーが自ら実行してしまう点が特徴です。感染後に情報送信・遠隔操作が行われることもあります。
スパイウェア/アドウェア
ユーザーの行動履歴や入力情報を収集するタイプ。ブラウザ拡張機能や無料ソフトに偽装して拡散します。個人情報の漏えいリスクが高く、企業利用端末では特に注意が必要です。
ランサムウェア(Ransomware)
感染端末のファイルを暗号化し、復号のための「身代金」を要求するタイプ。近年では暗号化と同時に情報流出(二重恐喝)を行うケースも増加。
2024〜2025年には「LockBit」や「BlackCat」などの新亜種が確認されています。
ルートキット/バックドア/ボットネット
ルートキットはOSの深層部に潜み、検知を回避するタイプ。バックドアは外部からの遠隔アクセスを可能にする機能です。
複数端末をボット化してDDoS攻撃に利用する「ボットネット」も企業の脅威となっています。
最新型(ファイルレスマルウェア・AI悪用型)
近年はファイルを生成せず、メモリ上で動作する「ファイルレス型」が主流化。従来のウイルス対策ソフトでは検出が困難です。
さらに、AI技術を悪用してセキュリティ検知を回避する「自己学習型マルウェア」も確認されています。
マルウェアの感染経路
メール添付ファイル・フィッシングリンク
最も一般的な経路がメールです。
件名や送信者を偽装した「なりすましメール」に添付されたZIP/Excel/PDFを開くことで感染します。最近ではマクロ機能を利用した感染型が主流です。
偽ソフトウェア・不正なダウンロードサイト
正規アプリを装う偽サイトからのダウンロード、クラック版ソフトの利用も感染リスクが高いです。攻撃者は検索広告を悪用し、公式サイト風のページを作成する手口も増えています。
USBメモリ・共有フォルダ経由の感染
社内ネットワークで共有フォルダを介した感染や、持ち込みUSBによる拡散も依然多いです。業務委託先や外部業者経由の感染も注意が必要です。
ゼロデイ攻撃・脆弱性の悪用による侵入
ソフトウェアの未知の脆弱性(ゼロデイ)を突く攻撃も増加中。OSやブラウザ、VPN装置など、更新が遅れたシステムは格好の標的となります。
感染の兆候と検知方法
パフォーマンス低下・不審な通信の確認ポイント
感染初期には以下の兆候が見られることが多いです。
- PCの動作が急に重くなる
- 不明なプロセスが常駐
- 外部との不審な通信(DNSクエリなど)
- システムログに不正アクセスの痕跡
早期発見にはログ監視やプロセス監査が不可欠です。
ログ分析・ネットワーク監視による異常検知
SIEMツールやSyslogを活用し、通信パターンの変化を可視化します。特にC2通信(攻撃者との通信)を検出できる仕組みを導入することが効果的です。
EDR/XDRツールによる自動検知
EDR(Endpoint Detection and Response)やXDRは、端末上の挙動をリアルタイムに監視し、不審な動作を自動検知・遮断する仕組みです。近年はAIによる異常検知アルゴリズムが強化されています。
サンドボックス環境での動的解析
未知のファイルを隔離環境(サンドボックス)で実行し、挙動を確認することで感染有無を判定できます。SOCやCSIRTでは標準的な解析手法です。
マルウェア感染時の対応・除去手順
感染端末の隔離とネットワーク遮断
感染が疑われたら、まずLANケーブルを抜き、Wi-Fiを切断してネットワークから隔離します。これにより二次感染や情報流出を防止します。
ウイルススキャン・駆除ツールの利用
信頼性の高いセキュリティベンダー(Microsoft Defender、ESET、Trend Micro等)のツールでフルスキャンを実施します。
検知されたファイルは隔離・削除し、システム全体を再起動して再スキャンします。
システム復旧・バックアップからのリストア
ランサムウェア感染などでファイルが破壊された場合は、感染前のバックアップから復旧します。バックアップはオフライン保存が重要です。
被害報告と法的対応(情報漏えい時)
個人情報や顧客データが流出した場合、個人情報保護委員会への報告や、関係者への通知義務が発生します。
CSIRT体制を整え、法務部門・広報部門と連携して迅速に対応しましょう。
企業におけるマルウェア対策と運用管理
多層防御(エンドポイント・ネットワーク・メール)
1つの防御では不十分です。
- エンドポイント:EDR/ウイルス対策ソフト
- ネットワーク:ファイアウォール/IDS/IPS
- メールゲートウェイ:スパム・フィッシング対策
- クラウド層:CASBやSASEで統合管理
複数レイヤーで守る「Defense in Depth(多層防御)」が基本戦略です。
パッチ管理・脆弱性対応プロセスの構築
OS・アプリの更新遅延は最も多い攻撃入口です。
定期的なパッチ適用スケジュールを策定し、脆弱性情報(JVN、CVE)を常にモニタリングする体制を整えましょう。
ゼロトラストセキュリティの実装
「すべての通信を信頼しない」というゼロトラストモデルの採用が進んでいます。
アクセス認証・デバイス検証・動的ポリシー適用を組み合わせ、内部脅威にも対応できる環境を構築します。
セキュリティ教育とフィッシング対策訓練
人的ミスが感染の7割を占めるといわれます。
全社員を対象に定期的なセキュリティ教育・疑似フィッシング訓練を実施し、「クリックしない文化」を育てることが重要です。
最新マルウェア動向とトレンド【2025年版】
AI生成型マルウェア・自動拡散型の台頭
生成AIを悪用したマルウェアが登場。AIが防御パターンを学習して自動的にコードを変異させ、検知を回避します。
国家支援型攻撃(APT攻撃)の増加
地政学リスクの高まりにより、国家支援型のAPT(Advanced Persistent Threat)が活発化。特に重要インフラや防衛関連企業が標的となっています。
クラウド・SaaSを標的とした攻撃の特徴
クラウド環境では認証情報の奪取が狙われます。
APIキーの窃取や権限昇格を目的とする攻撃も増加しており、CASBやIAM監査が不可欠です。
今後の防御戦略とセキュリティ製品の進化
EDRからXDR、さらにAI分析を統合したMXDR(Managed XDR)へ進化。クラウドネイティブな可視化基盤が求められています。
また、脅威インテリジェンスの共有(CTI)による組織横断的防御も注目されています。
まとめ|マルウェア対策は「技術」と「運用」の両輪で考える
個人・企業が実践すべき基本対策
- OS・ソフトを常に最新化
- 不審メール・添付を開かない
- セキュリティソフト・EDR導入
- 定期的なバックアップ・復旧訓練
継続的な監視とインシデント対応体制の重要性
マルウェアは「防ぐ」だけでなく「発見し、対応する」フェーズも重要です。SOCやCSIRTによる監視体制を構築し、インシデント対応計画(IRP)を定期的に検証することが、被害最小化の鍵となります。
投稿者プロフィール

- スータブル・ソリューションズは日々のITに関するQ&Aから、ITインフラ周りの構築・保守サポートまでワンストップで対応します。IT化の信頼おけるパートナーとして貴社に最適なソリューションを提案し、課題解決にオーダーメイド型のサービスを提供します。
【有資格】
■事業免許
総務省 届出電気通信事業者 A-10-3067号
東京都公安委員会 事務機器商営業許可 第306660205689号
東京都 産業廃棄物収集運搬許可 第13-00-119879号
神奈川県 許可番号 01400119879号
■取得認証
情報セキュリティマネジメントシステムISO27001認証(登録番号 JUSE-IR-402)
情報処理支援機関「スマートSMEサポーター」(認定番号 第16号-21100052(18))
最新のコラム
 2025/12/15RPAとは?できること・メリット・導入方法を初心者向けにわかりやすく解説
2025/12/15RPAとは?できること・メリット・導入方法を初心者向けにわかりやすく解説 2025/12/15社内SEとは?仕事内容・年収・将来性をわかりやすく解説【未経験・転職向け】
2025/12/15社内SEとは?仕事内容・年収・将来性をわかりやすく解説【未経験・転職向け】 2025/12/15シングルサインオン(SSO)とは?仕組み・メリット・導入方法をわかりやすく解説
2025/12/15シングルサインオン(SSO)とは?仕組み・メリット・導入方法をわかりやすく解説 2025/12/15【初心者向け】ベーシック認証とは?仕組み・設定方法・解除手順をわかりやすく解説
2025/12/15【初心者向け】ベーシック認証とは?仕組み・設定方法・解除手順をわかりやすく解説