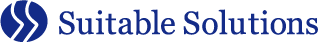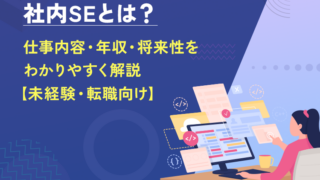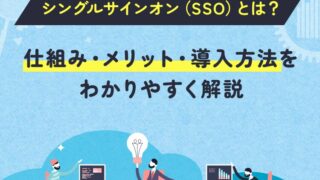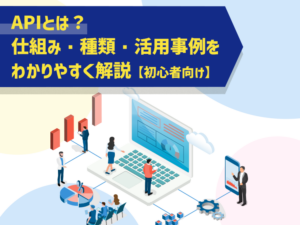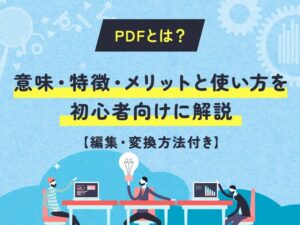ELTとは?ETLとの違い・仕組み・メリットをわかりやすく解説【データ基盤】
ELTとは?基本の意味と仕組み
ELTの定義(Extract, Load, Transform)
ELTとは、データ処理の手法のひとつで、「Extract(抽出)」「Load(ロード)」「Transform(変換)」の頭文字を取ったものです。従来のETL(Extract, Transform, Load)と異なり、データをまずデータウェアハウスやクラウド基盤に取り込み、その後に変換処理を行う点が特徴です。この仕組みにより、大量データを効率よく蓄積し、必要に応じて柔軟に加工できるメリットがあります。
データ分析基盤におけるELTの役割
近年のデータ分析基盤は、クラウドDWHを中心に構築されることが一般的です。ELTは、この基盤に大量のデータを迅速に取り込み、分析に適した形に変換する役割を担っています。特に、ログデータやマーケティングデータのように形式が多様で増加スピードが速いデータを扱う際に有効です。ELTにより、データサイエンティストやアナリストは必要なときに必要な変換を行い、即座に分析に活用できます。
なぜELTが注目されているのか
従来のETLはオンプレミス環境でのデータ処理を前提としていましたが、クラウドコンピューティングの進化によって状況が大きく変わりました。クラウドDWHは大規模かつ安価に計算リソースを利用できるため、ロード後に変換する「ELT方式」が効率的になったのです。また、データの鮮度を保ちながら柔軟な活用を実現できる点から、多くの企業がELTを採用しています。
ELTとETLの違い
処理の順番と考え方の違い
- ETL:データを抽出 → 変換 → 格納
- ELT:データを抽出 → 格納 → 変換
ETLではDWHにロードする前に変換が行われますが、ELTではまずDWHにデータをそのまま取り込み、必要に応じて変換処理を実行します。これにより、分析基盤上での柔軟な変換が可能となります。
従来のETLの課題
- データ量が増えると処理時間が長くなる
- 前処理に時間とコストがかかる
- 分析要件が変わるたびにETLパイプラインを修正する必要がある
このような課題により、ビジネス要求に即応できないケースが多く発生していました。
ELTがETLに優るケース
- クラウドDWHを活用する場合:高いスケーラビリティを持つため、大量データの処理が可能
- 柔軟な分析を行いたい場合:後から変換ルールを変更できるため、探索的分析に向いている
- リアルタイム性が求められる場合:まずデータを格納することで、即時利用が可能
これらの点で、現代のデータ分析基盤にはELTの方が適しているといえます。
ELTのメリットとデメリット
メリット(柔軟性・スケーラビリティ・コスト効率)
- 柔軟性:変換処理を後から行えるため、要件変更に強い
- スケーラビリティ:クラウド基盤の計算能力を活用し、大量データを短時間で処理可能
- コスト効率:従来の専用ETLサーバーが不要で、クラウドリソースを従量課金で利用できる
これらの特性により、急速に成長するビジネスやスタートアップに適したアーキテクチャといえます。
デメリット(変換処理の複雑さ・クラウド依存など)
- 変換処理が複雑化:分析要件が高度になるとSQLやスクリプトの管理が難しくなる
- クラウド依存:オンプレ環境では恩恵が少なく、クラウド基盤への依存度が高い
- コスト予測の難しさ:従量課金モデルのため、利用状況によってはコストが高額化する可能性がある
導入前にはこれらのリスクも十分に検討する必要があります。
ELTを支える代表的なツール
クラウドDWH(Snowflake, BigQuery, Redshift)
- Snowflake:マルチクラウド対応で拡張性が高い
- BigQuery:Googleのサービス群との連携が強力
- Redshift:AWS環境と親和性が高く、幅広い利用実績
これらのクラウドDWHがELTの基盤を支えています。
ELT専用ツール(Fivetran, Airbyte, dbt)
- Fivetran:SaaS型のデータ連携ツール。ノーコードで各種データソースと接続可能
- Airbyte:オープンソースで拡張性が高い。コミュニティ主導でコネクタが充実
- dbt:変換処理に特化したフレームワーク。SQLベースでモジュール管理が可能
これらを組み合わせることで効率的なELT基盤を構築できます。
オープンソースと商用の違い
- オープンソース:初期コストを抑えやすいが、運用負荷が高い
- 商用ツール:サポートや管理機能が充実しており、安心して利用できる
組織のリソースやスキルに応じて選択することが重要です。
ELTの活用事例
マーケティングデータ統合(広告・CRM・MA)
広告配信データ、CRM(顧客管理)、MA(マーケティングオートメーション)ツールのデータを統合し、キャンペーン効果を横断的に分析できます。これにより、LTV(顧客生涯価値)の最大化や広告予算の最適化が可能になります。
IoTやログデータの分析基盤
IoTデバイスやWebサービスのログは、膨大で非構造的なデータが多く含まれます。ELTを活用すれば、まず大量のログをDWHに蓄積し、必要に応じて変換することで柔軟な分析が実現できます。
機械学習用データパイプライン
機械学習モデルの学習には多種多様なデータが必要です。ELTを利用すれば、データを一元的に集約し、特徴量エンジニアリングや前処理を柔軟に行うことができます。これにより、モデル精度の向上や実験のスピードアップにつながります。
ELTを導入する際のポイント
データ基盤の選び方
- 利用するクラウド環境(AWS, GCP, Azure)との親和性
- スケーラビリティとコストモデル
- ツールとの統合性
これらを考慮して、自社に最適なDWHを選択することが重要です。
セキュリティとガバナンスの考慮
- データアクセス権限の適切な管理
- 暗号化や監査ログの活用
- コンプライアンス(GDPR, 個人情報保護法など)への準拠
セキュリティとガバナンスを確立することで、安全で信頼性の高いデータ基盤が構築できます。
小規模から始める導入ステップ
- まずは一部のデータソースを対象にパイロット導入
- 成果を確認しながらスケールアップ
- 運用フローを整備し、本格的に全社展開
このように段階的に導入することで、リスクを抑えながら効果的な基盤構築が可能です。
まとめ
ELTを理解することで得られる価値
ELTを理解すれば、大量データを効率的に扱い、柔軟な分析や新たなビジネス価値創出につなげられます。従来のETLに比べて迅速かつスケーラブルなデータ基盤を構築できる点が大きな魅力です。
今後のデータエンジニアリングの潮流
クラウドDWHの進化、SaaSツールの普及、機械学習の拡大により、ELTは今後さらに主流となるでしょう。データエンジニアやアナリストを目指す人にとって、ELTは必須スキルであり、企業にとっても競争力を高める鍵となります。
投稿者プロフィール

- スータブル・ソリューションズは日々のITに関するQ&Aから、ITインフラ周りの構築・保守サポートまでワンストップで対応します。IT化の信頼おけるパートナーとして貴社に最適なソリューションを提案し、課題解決にオーダーメイド型のサービスを提供します。
【有資格】
■事業免許
総務省 届出電気通信事業者 A-10-3067号
東京都公安委員会 事務機器商営業許可 第306660205689号
東京都 産業廃棄物収集運搬許可 第13-00-119879号
神奈川県 許可番号 01400119879号
■取得認証
情報セキュリティマネジメントシステムISO27001認証(登録番号 JUSE-IR-402)
情報処理支援機関「スマートSMEサポーター」(認定番号 第16号-21100052(18))
最新のコラム
 2025/12/15RPAとは?できること・メリット・導入方法を初心者向けにわかりやすく解説
2025/12/15RPAとは?できること・メリット・導入方法を初心者向けにわかりやすく解説 2025/12/15社内SEとは?仕事内容・年収・将来性をわかりやすく解説【未経験・転職向け】
2025/12/15社内SEとは?仕事内容・年収・将来性をわかりやすく解説【未経験・転職向け】 2025/12/15シングルサインオン(SSO)とは?仕組み・メリット・導入方法をわかりやすく解説
2025/12/15シングルサインオン(SSO)とは?仕組み・メリット・導入方法をわかりやすく解説 2025/12/15【初心者向け】ベーシック認証とは?仕組み・設定方法・解除手順をわかりやすく解説
2025/12/15【初心者向け】ベーシック認証とは?仕組み・設定方法・解除手順をわかりやすく解説